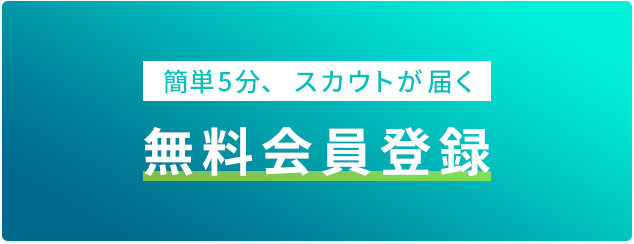CREATOR INTERVIEW VOL.163
見た目だけが「デザイン」じゃない。誰もが使える「設計」目線で考え、情報格差のない社会へ


Torque Inc.
アクセシビリティとは何か。なぜWebサイトをつくるのか。そんな本質的な問いに向き合い続けるトルク。代表の本田一幸氏が語る、トルクのカルチャーとは。
「デザインの力で情報格差をなくす」というミッションを掲げる株式会社トルク。同社は2020年に本田一幸氏が創業したデジタル領域を専門とするクリエイティブ・テック企業です。Webサイト構築、アクセシビリティコンサルティング、モダンフロントエンド開発などを手掛け、特にWebアクセシビリティと最新のエンジニアリング技術に強みを持ちます。 今回は同社を創業した本田一幸氏にインタビュー。強みとしているアクセシビリティの考え方や、大切にしているミッションへの思い、求めている人物像などを聞きました。
高いアクセシビリティとは、支援技術が正しく動くこと。エンジニアリングこそがその要
多くの競合がひしめくWeb制作業界で、トルクはどんな点を強みにしているのでしょうか。
当社では、高品質なクリエイティブはもちろんのこと、障害者や高齢者を含むすべての人が必要な情報にアクセスできる、アクセシビリティの高いWebサイト構築における豊富な経験とノウハウを強みとしています。
欧米をはじめとした海外ではWebサイトのアクセシビリティ対応が進んでいる一方、日本国内での認知度は決して高くはありません。しかし近年、アクセシビリティに取り組むべきだというお客様の意識は確実に高まっています。2024年に障害者差別解消法が改正・施行され、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化されたことで、スタートアップから大企業まで多くの企業が自社サイトのアクセシビリティ向上を検討する機運が高まっています。
もちろん、法改正とは関係なく、以前から熱心に取り組んできた企業もあります。特にグローバル市場で活動する企業やユニバーサルなサービスを提供する企業は、インターネットの黎明期からアクセシビリティの高いWebサイト構築を前提としています。
当社では、こうした動きが起こる以前からアクセシビリティの必要性を認識し、その実装に注力してきました。どうすれば使いやすさを追求できるか、デザイン性を損なわずに利便性を高められるかを常に考え、デザインとアクセシビリティの両立を模索してきました。こうした経験やスキル、そしてお客様の要望に応えてきた実績こそがトルクの強みだと自負しています。

自治体などの公的機関はアクセシビリティに対する意識が高く、早期に対応しているイメージがあります。
自治体などの公的機関は、サービスをすべての国民に提供しなければならないため、以前から積極的に取り組んでいます。総務省は2005年に「みんなの公共サイト運用モデル」(現在は「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に改訂)を策定しており、これは実質的にウェブアクセシビリティ運用のためのガイドラインと言っても過言ではありません。
しかし、多くの公的機関が定量的に評価可能なアクセシビリティを高めようと対応を進めた結果、定量的な評価が難しいユーザビリティやデザイン性が損なわれてしまうケースも少なくないのが現実です。アクセシブルで開かれたWebサイトでありながら、多くの人にとって使いづらいという問題が生じてしまっています。
ただし最近では、アクセシビリティを確保しつつ、見やすさや使いやすさにも配慮した公的機関のWebサイトも少しずつ増えてきました。アクセシビリティとユーザビリティ、そしてデザイン性を両立させようという機運が高まっているのは、良い傾向だと感じています。
最近は自治体に留まらず、文字の大きさや表示色を自由に変えられる仕組みを実装するWebサイトも増えてきたと感じます。こうしたアクセシビリティに対応する動きをどのように感じますか。
そもそも、多くの人がアクセシビリティを誤解していると感じています。例えば、「文字サイズを大きくしなければならない」「文字サイズを大・中・小から選べるようにしなければならない」といった考え方は、必ずしもアクセシビリティとイコールではありません。
同様に、最近では「アクセシビリティオーバーレイ」と呼ばれる、後付けでアクセシビリティ機能を追加するツールも見かけますが、これらも根本的な解決にはなりません。むしろ、既存の支援技術と競合したり、ユーザーが普段使い慣れている操作を妨げたりすることさえあります。
高齢者がスマートフォンを使う際、OSやブラウザの機能で文字サイズを大きく設定していることが多いですよね。アクセシビリティに求められるのは、そうしたOSやソフトウェア、デバイスなどの支援技術を使っているユーザーが、思い通りに機能を使えるようにすることが第一です。表面的な機能追加ではなく、Webサイトの構造自体を適切に設計することが重要なのです。
文字のサイズを変えられる機能があるかよりも、いかに支援技術が問題なく利用できるかが重要だと。
例えば、文字サイズを切り替えるボタンの位置や大きさは、制作者が勝手に決めた値に過ぎません。支援技術を使いたいユーザーにとっては、その位置やサイズでは使いづらいかもしれませんし、支援技術の正しい動作を阻害することさえあります。
当社では、一人でも多くの人がストレスなく必要な情報にアクセスできるよう、アクセシビリティ向上に主眼を置いています。そしてそれは我々にとって重要な「デザイン」の対象だと考えています。障害者や高齢者を含むすべての人にとって使いやすく、快適に情報にたどり着き、必要な機能を利用できるか。これをデザインとテクノロジーの力でどう解決し、どう具現化するか。こうした課題に私たちは常に向き合っています。ユーザーの利便性や使いやすさを損なわないデザインと向き合い続けてきたからこそ、どちらも損なわないWebサイトを制作できるのだと考えます。

そのほかにトルクとしてWebサイト制作でこだわっていることはありますか。
HTMLを中心にソースコードの品質を高く保つこと、そして最新のフロントエンド技術でプラスの価値を提供することを非常に重要視しています。ソースコードの品質の高さは、突き詰めると最終的に必ずアクセシビリティの高さに行き着きます。アクセシビリティを高めるためには、HTMLのタグを正しく使う必要があるためです。
Webサイトの中には、見た目の華やかさや実装コスト削減のために、意味的に適切ではないタグを使い、CSSで装飾しているものが少なくありません。しかし、それではスクリーンリーダーなどの支援技術がWebサイトの構造や内容を正しく認識せず、伝えたい内容をユーザーに正しく伝えられません。現在のHTML標準仕様(HTML Living Standard)に沿って正しくマークアップすることで、コードの品質は自然と担保されます。
こうした構造設計も含めて全体をデザインできるのが、トルクの強みでありこだわりです。そして、モダンなフロントエンド技術を駆使しながら、高いアクセシビリティを実現できるエンジニアリングこそが、私たちの価値の核心なのです。
真面目で素直に、目の前のお客様と課題に向き合える人を採用したい
採用についてお聞きします。スキルや実績、経験以外の要素で重視することや、求めている人物像などあれば教えてください。
何より誠実であることです。誠実でなければお客様の信頼は得られません。そして信頼を得るためには、まず私たちがお客様を信頼することも大切だと考えています。
明るく心を開いて接することができるかどうかも大切です。人として当たり前のことかもしれませんが、中には恥ずかしさから内にこもってしまう方もいます。その気持ちも理解できますが、これから変わりたい、変わることができると思っている方、実践できる方にぜひ来ていただきたいです。
マネージャーやシニアクラスの方も積極的に募集していると聞きました。具体的なスキルや経験などの条件はありますか?
特にありません。ある程度の実績と経験があり、それを証明できる方であれば問題ありません。
ただ、シニアクラス以上の方がご入社されても、いきなり部下を持つことはありません。給与面はシニアクラス相応の待遇となりますが、最初はリーダーポジションとしてチームに馴染んでいただき、業務に慣れていただきます。一定の実績を積んだ後に、適切なポジションに昇進していただく形になります。
応募者の中からトルクに合う人材を見極めるのは難しいと思います。面接時に工夫していること、注意していることはありますか?
面接はリモート1〜2回、対面1〜2回の原則3回、多い場合で4回程度を実施し、お互いのミスマッチがないように慎重に判断するよう心掛けています。その際、経験年数や経歴だけをもとに採否を決めないよう努めています。中には業界の有名企業で活躍し、多くのプロジェクトを手掛けたという素晴らしい経歴をお持ちの方から応募をいただくこともあります。しかし、これまでの経歴がすべてだとは思いません。お見送りとさせていただく場合もありますし、未経験でもポテンシャルを評価して採用させていただくことも何度もあります。
私たちは、応募者の方に誠実さを求める以上、私たち自身も可能な限り誠実でなければならないと考えています。給与面や制度、キャリアパス、お客様との向き合い方についてなど、できる限りオープンに、フランクに何でもお話しさせていただいています。
トルクで働かれているスタッフを見て、共有している姿勢や考え方などあれば教えてください。
能力が高いことはもちろん、個性的で魅力溢れる人が本当に多いという印象です。そんな中でも共通しているのは、やはり誠実で実直な方が多いということですね。多くのスタッフが取引先やお客様から「トルクさんらしい」と言われることも増えてきました。それだけトルクの仕事に対する姿勢やデザイン、エンジニアリングの考え方などが、スタッフ一人ひとりに根付きつつあるのだと思います。
クリエイティブ企業と聞くと、型にはまらない個性豊かで我の強い人が多いというイメージを持たれるかもしれませんが、トルクのスタッフは良い意味でとても真面目です。仕事に誠実に真摯に取り組むスタッフばかりです。トルクでは、そんなスタッフの真剣さを社内で感じられます。
ちなみに、トルクのデザイナーたちはアクセシビリティとユーザビリティを両立させながら、かつ美しく実装・開発を考慮したグリッドデザインを得意としています。エンジニアたちは最新のフロントエンド技術を駆使し、このデザインを最高の品質で実現する高度な実装を追求しています。それも、もしかしたら社員一人ひとりの姿勢がデザインに現れているのかもしれませんね。

Webサイトに掲載されている社員のみなさんの写真を見ると、クリエイターという側面より、真剣さや真面目さ、仕事への愚直な姿勢を感じ取ることができますね。
もしかすると、クリエイティブ企業でデザインに携わっているというより、スタートアップやベンチャー企業で色々なことにチャレンジする人が集まっている状態に近いのかもしれませんね。私たちはデザイナーやエンジニア、ディレクターといったWeb制作会社によくある職種の固定観念にとらわれず、それぞれが最高のプロフェッショナルとして最高の仕事と価値をお客様と社会に提供し続け、お客様と共に、そして社員個々人も成長していきたいと考えています。こうした考えに共感し、スタートアップ企業からも欲しがられるような、何事にも真摯に挑戦する姿勢を持つ意欲的な方にぜひ来ていただきたいです。
「失敗してもいい」そう思えるようなバリューに
トルクのミッション・ビジョン・バリューについて教えてください。
当社のミッションは「デザインの力で情報格差をなくす」です。私たちは「デザイン」という言葉を非常に広義に捉えています。本来デザインとは「設計」という意味を含み、単なる見た目の部分にとどまりません。お客様の意思や意図、そこから生まれる言葉、そしてそれを形作るプログラムやシステム、マークアップコードなども含め、すべてデザインの対象だと考えています。
その上でアクセシビリティもまた、非常に重要なデザインの対象です。いかにアクセシビリティを高め、この社会から情報格差をなくすか。これこそが、私たちが提供するデザインそのものの価値の一つだと考えています。お客様のWebサイト制作を通じて、お客様と共に情報格差のない社会の実現を目指していきたいと思っています。
バリューについても教えてください。
バリューは9つあり、当社の行動指針となっています。具体的には、「お客様と同志である」「ベストプロフェッショナル」「早いが正義。行動第一」「なぜ?から考え行動する」「権限のない責任、責任のない権限、どちらも存在しない」「楽しさを見つけ出す天才」「失敗できたらおめでとう」「与えることに躊躇しない」「細部に宿らせる」です。
例えば、「なぜ?から考え行動する」について。Webサイトのリニューアルのご相談をいただく際、私たちは常に「なぜリニューアルするのか」という根本的な部分から考えるようにしています。Webサイトを作ること自体が目的化しないためです。時には、リニューアル以前に社内の運用体制を見直す方が効果が高いと確信すればそちらをご提案することもありますし、採用サイトを作る前に採用戦略から考え直すべきとお伝えすることもあります。常に本質的な目的である「なぜ?」を追求することが、お客様からの信頼に繋がると信じています。
「与えることに躊躇しない」は、常に人に与えることの大切さを表しています。何か「欲しいものを得る」ことで得られる幸福は、それを手に入れた瞬間がピークになりますが、人に与えることで得られる幸福は、その時だけでなく、その後もずっと長く続きます。むしろ、時間の経過とともに思い出となってさらに増していくことさえあります。つまり、自分たちが幸せになるためには、何かを得ようとするよりも、お客様や仲間をはじめ、周囲の人々を幸福にするために何ができるのかを考え続け、実行し続けることが近道なのです。そうであれば、人に与え続けることに躊躇する理由はありません。こうした考えからこの言葉を、バリューにしました。
社員にミッションやバリューを浸透させるため、どのような取り組みをしていますか?
定期的な全社会はもちろん、毎日の朝礼でも私からミッション、バリューについて話しています。さまざまな話題を話す中でも必ずミッションやバリューに通じるようにし、できる限り形骸化しないよう、みんなが身近に感じられるよう意識しています。ちなみに、応募者の方や新入社員にも必ずミッション、バリューの考えを説明する時間を設けるようにしています。トルクにとってはそれだけ大切で、礎を成す考え方だと捉えています。
企業規模の拡大とトルクの個性の両立を目指したい
今後の展望を教えてください。
トルクという会社の魅力や価値をこれからも損なうことなく、より色濃く示していければと考えています。クリエイティブを提供する企業は、一般的にブティック型の少数精鋭の企業が多く、社員を増やしすぎるとクオリティを担保できなくなり、凡庸な成果物しか生み出せなくなると考えられていることも少なくないかと思います。企業規模が大きくなるほど、クリエイティブ企業としての魅力が失われていくと感じる人も多いのではないでしょうか。
しかしそんな中でも、規模の拡大とトルクの価値の最大化を両立していければと考えています。当社には、さまざまな才能が集まっています。個性を大切に育み、他社では作れないクリエイティブを生み出すスタッフが揃っています。この強い個の力をいかに組織の強さに転化していくことができるかが今後の重要なテーマだと考えています。
規模の大きな企業でありながら、デザインやエンジニアリングの高いクオリティを維持している会社も複数存在しますし、個々の社員が個性豊かな魅力を放ち続ける事例も多くあります。会社として社員一人ひとりの個性や考えを大切にし、社員が増えても個性を尊重し続けることが重要だと思っています。これまで育んできたトルクのカルチャー、そして社員一人ひとりの価値を今後も見失わずに高めていくことで、社員数が増えて規模が大きくなっても、トルクの魅力はますます増していくのだと信じています。
個性が確立されていれば、トルクの魅力が希薄になることはないのですね。
クリエイティブやデザインといっても、エッジの効いた表層的にかっこいいものやおしゃれなものだけが優れているわけではありません。使いやすい設計や公共性の高いデザインも重要です。ユニバーサルデザインやアクセシビリティを重視しながら、すべての人にとって使いやすい体験をお客様と共に創造していくことこそが、成長への道だと思っています。トルクという会社の個性や魅力も、より引き立たせられるのではないでしょうか。
デザイナー、エンジニア、ディレクター、それぞれの専門性を活かしながら、アクセシビリティという共通の目標に向かって挑戦し続ける。そんな仲間とともに、トルクの未来を築いていきたいです。
モダンなフロントエンド技術で高いアクセシビリティを実現したいエンジニア、美しいだけでなく、インクルーシブでユニバーサルなデザインを追求したいデザイナー、本質的な課題解決を目指すPM、ディレクター。そんな志を持つ方々をお待ちしています。