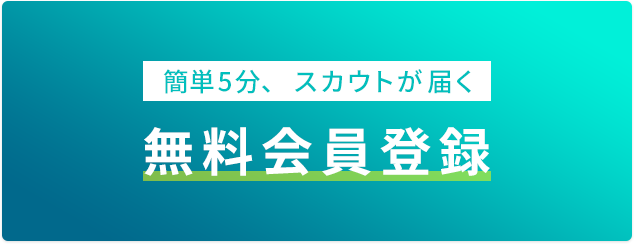CREATOR INTERVIEW VOL.196
「働きやすさ」と「やりがい」は両立できる。教育業界を支えるWeb制作会社 コーディアの社員が語る仕事の楽しさと未来の描き方
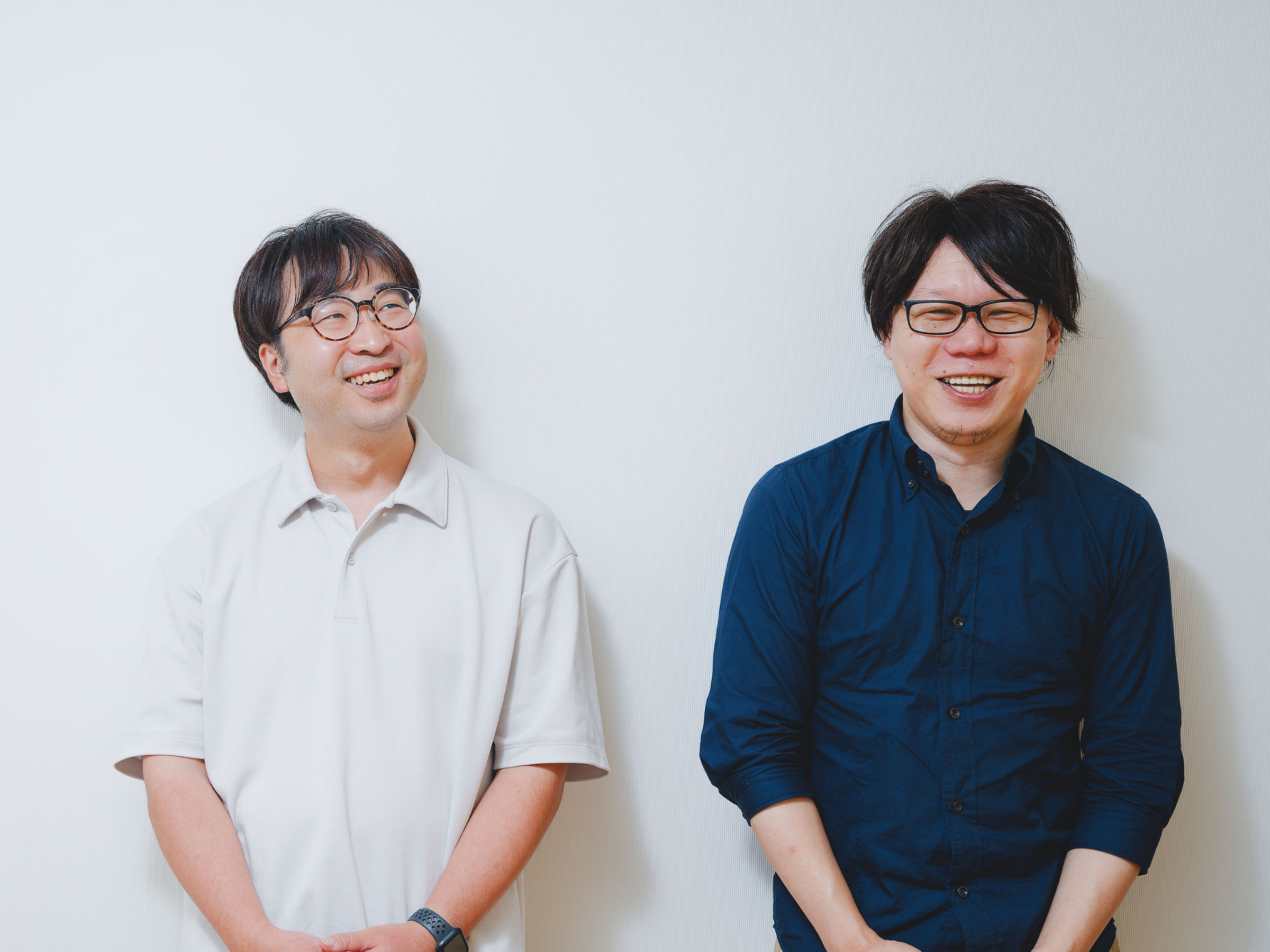

コーディア株式会社
追いかけるのはトレンドより「安心感」。教育の未来に寄り添うWeb制作の真髄
Web制作会社と聞くと、多忙な毎日を想像するクリエイターは少なくありません。しかし、「基本は定時退勤」と語る制作会社があります。それが、教育業界に特化したWebサイト制作を手がけるコーディア株式会社です。 今回はディレクターチームを率いる執行役員でディレクターの荻島健さん、ディレクターの中井健太郎さん、ディレクターのRさん、そして未経験から挑戦しているディレクターのMさんという、経歴も経験年数も異なる4名にインタビュー。クライアントの課題に深く寄り添う仕事のやりがいから、クリエイターが安心して成長できる独自のカルチャー、「制作会社=激務」のイメージを覆す柔軟な働き方まで、コーディアのリアルな魅力をお聞きしました。
多様なキャリアが生み出す価値。私たちがコーディアを選んだ理由
まず皆さんがコーディアに入社された経緯と、現在の業務について教えてください。
荻島: 私はWebデザイナーとして15年ほどこの業界にいますが、10年前にディレクター専門としてコーディアに入社しました。現在はディレクターチームのリーダーとしてチームをマネジメントしながら、主に2つのディレクション業務を担っています。1つはクライアントに提案をする「営業」的な側面、もう1つは発注いただいた案件について要件を整理し、社内スタッフをアサインしながら公開まで導く「進行管理」の側面です。この2つが現在携わっている主な業務となります。
中井: 私も同じく、前職は制作会社でデザイナーをしていました。手を動かす中で上流工程から関わりたいという思いが強くなり、ディレクターとしてコーディアに転職して約5年目になります。
Rさん: 私は異業種からの転職組です。新卒ではネットワークエンジニアとして5年間、企業のネットワークセキュリティを構築する仕事をしていました。しかしクリエイティブな仕事への思いを諦めきれず、別の制作会社を経てコーディアに入社しました。最初はデザイナー志望でしたが「ディレクターの方が向いている」という意見をもらい、クライアントの成功に貢献するという本来の目的に立ち返ってディレクターの道を選びました。
Mさん: 私は2024年に入社したばかりで、もともと新卒では事務や受付を担当していました。コーディアの面接を受けた際に皆さんの人柄が大変よく、また未経験者へのサポートも手厚いとお聞きし、Webディレクターという道へ進むことにしました。コーディアなら安心して成長できると感じたのが入社の決め手です。

「利益」だけではない価値を追求する。教育業界特化の面白さと難しさ
次に業務内容についてお聞きします。教育機関のクライアントに特化しているとのことですが、一般企業向けのWeb制作とはどのような違いがありますか?
中井: もっとも大きな違いは、クライアントが追求するものは必ずしも「利益」でない点です。学校の先生や事務の方が窓口になることが多いのですが、担当される方々が見ているのは生徒や保護者のことで、どうすれば学校の良さが伝わるかという視点でお話をされます。そのため当社も同じ目線に立ち、一緒に伴走していく姿勢が求められます。そこが難しさでもあり、この仕事ならではの魅力ですね。
Webサイトを制作する上で、特に意識していることは何でしょうか?
中井: 奇抜さや流行りのデザインを追うよりも、Webサイトを見る学生さんや保護者の方が安心感を持てるかどうかです。そのため、実直で使いやすいUIやUXを何よりも大切にしています。一般的なWebサイトであれば最新トレンドや独自性を打ち出すものが多いかもしれません。しかし、教育関係のWebサイトであればこういった要素は必ずしも求められません。いかに安心感につながるか、さらに「この学校で何を学べるのか」といった本質的な部分が直感的に伝わるWebサイト設計を常に心がけています。
Rさん: 運用性の高さも意識していますね。学校の先生方は、Webサイトの更新業務を別の業務と兼任されているケースがほとんどです。できるだけ負担のかからない更新業務となるよう配慮しています。
担当の先生や職員の方が異動で入れ替わることも多いため、誰が担当になっても簡単に更新できることも非常に重要です。担当される方々の負担を減らしつつ、自由度の高い更新を実現するにはどうすれば良いか、いつも頭を悩ませていますね。ここが腕の見せどころでもあると思います。時には専門性が高すぎる大学の研究所のWebサイトを担当して、先生のお話を理解するのに必死になる、なんていう苦労もありますが(笑)。
荻島: 一般企業と違い、「予算300万円でいい感じのWebサイトを作ってほしい」というように、要望がふわっとしているケースも少なくありません。だからこそ、これまで数多くの教育機関のWebサイトを手がけてきた私たちの知見が活きます。「この学校であれば、こういう強みを打ち出してはいかがでしょうか」と課題を言語化し、方向性を示すところから関われるのは大きなやりがいにつながりますね。
一方、公共性が高いという業界の特性上、私立・公立を問わず、案件のほとんどがコンペティションで決まります。一度ご縁をいただくと、保守運用も含めて10年以上のお付き合いになることも珍しくありません。だからこそ、長期的な信頼関係を築けるような提案を常に心がけています。
残業は月10時間。制作会社のイメージを覆す柔軟な働き方
制作会社というと、どうしても多忙なイメージがあります。実際の働き方はいかがですか?
Rさん: 前の会社は残業も休日出勤も多かったので、コーディアに入社した時はなんて働きやすいんだろうと思いましたね。普段は定時で帰れますし、受験や入試時期に入る1月~3月の繁忙期も、残業が増えることはあるものの無理な働き方はありません。子育て中の社員も多く在籍していますが、お子さんの行事や急な体調不良で数時間抜けたり、お休みを取ることも柔軟に配慮してもらえる環境です。
Mさん: 本当に急なことでも柔軟に対応してもらえますし、休日出勤は一度もありません。休みも取りやすいので、プライベートとのバランスが取りやすいです。もちろん柔軟な働き方を許容してくれるからこそ、クライアント対応や制作物のクオリティ、スケジュールなどは自身でしっかりと管理する必要があると感じています。
「帰りにくい雰囲気」のようなものはないのでしょうか?
中井: まったくありませんね。「周りが残っているから自分も残らなきゃ」という空気は一切なく、自分の仕事が終われば気兼ねなく帰れます。この心理的安全性が、働きやすさにつながっているのだと思います。
荻島:コーディアには各々がどう働きたいかを尊重する文化が根付いています。就業時間は9時半から18時半ですが、月間の総労働時間で調整したり、「1日6時間勤務」といった個別の希望に対応したりすることも可能です。デザイナーやエンジニアはほとんどがリモートワークですし、ディレクターも週1回程度はリモートで働いています。個人の裁量で柔軟に働き方を調整できる環境ですね。
未経験でも安心。属人化を防ぐ「仕組み」と、成長を後押しする「文化」
未経験で入社された方も安心して働ける環境とのことですが、どういった支援や体制を整えていますか。

荻島: 当社は経験の浅い方も積極的に採用して育てていく方針なので、仕組みを整えることに力を入れています。代表的なのが、ディレクション業務を体系的にまとめた詳細なガイドラインです。これは、個人のやり方に依存する「属人化」を防ぎ、経験の浅いメンバーでも安心して業務を進められるように作ったもの。クライアントの打ち合わせで確認することや制作過程の具体的なフローなど、必要な作業を洗い出し、チェックできるようにしています。ディレクターだけでなく、デザイナーやエンジニア向けのガイドラインも用意し、チーム全体がスムーズに連携できる仕組みになっています。
中井: 私が入社して最初に驚いたのも、このガイドラインを使った「ドキュメント化」の文化でした。仕事の進め方やナレッジをきちんと文章で残しているため、キャッチアップが非常にスムーズでした。今でも課題が見つかるたびに皆で議論し、社内のナレッジとしてドキュメントを更新していく文化が根付いています。
Rさん: Web業界の専門用語集や見積もり項目のリストなど、新人の方がつまずきやすいポイントをまとめた資料もあったため、私も入社当初は大変助かりました。ベースとなる知識をすぐに参照できるため、安心して業務に取り組めます。
こういった社内のナレッジも現場の皆さんで更新する、ボトムアップで進める空気感なのですね。
荻島: そうですね。この業界ならではかもしれませんが、新しい技術トレンドを追い続ける姿勢を失ってはならないと感じています。それを支えているのは現場からの自発的な行動です。例えば最近はAIが流行っていますが、ChatGPTを使って業務効率を高めるアイデアを現場の誰かが提案するようなイメージですね。上から言われて動くのではなく、現場で出た意見から社内のルールやナレッジが更新されていくのは、コーディアという会社の企業風土に他なりません。
中井: デザイナーやエンジニアも、ただ指示を待つのではなく「もっとこうした方が良い」と積極的に意見を出し合っています。役職や職種に関係なく、全員でより良いものを作っていこうというフラットな関係性も、当社の強みだと思います。
コーディアで輝ける人とは?「伴走」が大きなキーワード
ずばり、どのような方と一緒に働きたいですか?
中井: クライアントの課題を自分ごととして捉え、一緒に解決策を模索できる「伴走力」のある方ですね。コーディアの仕事は、「これを作ってください」とすでに要件が決まった状態で進める案件がほとんどありません。クライアントの課題を汲み取ったうえで、「もっと良くするためにこうしませんか」と能動的に関われる方が向いています。
Rさん:どんな人とも誠実に向き合い、相手に共感し、伴走できる方です。コーディアのクライアントはWebの専門家ではありません。「何に困っているかさえ分からない」という方もよくいます。ガツガツと提案を押し通すのではなく、「なるほど、そこでお困りなのですね」と、同じ目線で対話を進められる方がフィットすると思います。
未経験の方であれば、分からないことは「分からない」と素直に言える方が好ましいですね。たったその一言を言えるかどうかが大切です。自分で抱え込まず、分からないことを相談して解決しようとする姿勢を持っている方なら伸びしろがあり、社内の雰囲気ともマッチするでしょう。
Mさん: 相手の立場に立って考えられる方です。クライアント自身も気づいていない本質的な課題を根気強いヒアリングで見つけ出すことがコーディアの業務では求められます。クライアントと一緒に課題を探し、解決に導くまでのプロセスを楽しめる方なら、きっと活躍できるはずです。
母校のサイト制作も実現。クリエイターとして描く、私たちの未来
最後に、皆さんが今後コーディアで挑戦したいことや、仕事のやりがいを教えてください。
Rさん: ご存じのように教育業界は少子化が加速し、生徒の奪い合いが過熱しています。今後、学校の「独自性」や「特色」をどうWebサイトで表現するのかという重要性がますます高まっていくでしょう。だからこそ、クライアントがまだ気づいていない魅力を引き出せるようになりたいですね。Webサイトを通じてそれぞれの学校ならではの強みを、社会に伝えられるような挑戦を続けたいです。
Mさん: まずはディレクターとして一人前になり、将来的にはWebサイトの企画から携わるような人材を目指しています。多くのクライアントが抱える課題の解決に貢献し、いずれは「コーディアだからお願いしたい」と言っていただけるような、信頼される存在になることが目標です。

中井: 私はコーディアで、自身の出身中学・高校、大学の学科のWebサイトリニューアルに携わるという貴重な経験をさせてもらいました。特に大学の案件は、自らアプローチして実現したものなんです。自分がかつて青春時代を過ごした学び舎の価値を自身の手で創出できたのは、この仕事ならではの大きなやりがいでした。これからも長くお付き合いのあるクライアントのWebサイトを更に良くするため、改善提案により注力していきたいですね。
Rさん: クライアントから「オープンキャンパスの申し込みがすごく増えました」や「保護者からの評判も良いです」といった声をいただいた時は、本当に嬉しいですね。自分たちの仕事が貢献できていると実感する瞬間こそ、大きなやりがいを感じます。
今後も未来の学校、さらに教育業界を支えられるような仕事に携わっていきたいと思っています。